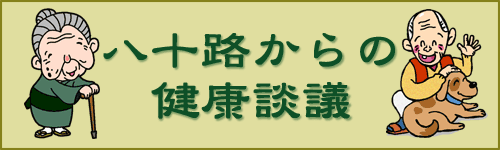|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. 我々の寿命は何処まで延びるか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初期の予測は、平均寿命の伸びは主に幼児死亡率の減少によるから限界があるのは当然ということでした。しかし最近では高齢者の死亡率も下がっています。それでも多くの予測ではこの低下も段々と限界に近づくに違いないと考えているようです。 さて著者らは先ず1840年から2000年までの世界中から集められるだけ集めた各年度ごとの女性の最高の寿命を、横軸に年をとってプロットすると見事な直線になり160年間に40年の延長が見られそれが統計上極めて確かなもの(r2=0.992)であることを見つけました。日本の平均寿命は初めは遥かに下の方にありましたが、この直線の最後の20年位は殆ど日本のデータです。その前にはIcelandのものがかなりの部分を占めています。男性についても同様の結果が得られています。ただこのときは日本とIcelandのデータが入り混じっています。これに対してアメリカは、1900年には最高から10年も下にあったのが1950年には1年以下まで追いついたのですが、2000年にはまた5年程下になってしまいました。この直線は2020年、2040年と真っ直ぐに伸びると考えてよいのではないか、と言うのが彼らの主張です。私は日本の平均寿命のデータを見ながら何時伸びが止まるかと心配しながら見ていましたが、今のところ未だ伸び続けているようです。 著者らは、色んな人の予測が何時ごろどの国のデータで破られたかを面白い表にして示しています。但しこれはScienceの論文にはなく、インターネットで読める補足資料にあるものです。最初のDublinですが、彼が1928年に64.8歳という最高寿命の予測をしたときには、New Zealandでは既に1921年に女性の平均寿命が65.93年に達していたことを知らなかった、ということです。科学者だけでなく、国連とか世界銀行といった国際機関の予測も次々と破られています。 平均寿命が何処まで延びるかは長寿国日本にとってはいろんな意味で大きな問題です。個人としても、また社会としてもしっかりとした予測を立て、それへの対策を考えていくために研究の現状をご紹介しました。
表: 最高寿命(限界)の予測とそれを越す寿命を示した年と国
** 50才の平均余命が35年を越えないものと予測。 * Jim Oeppen and James W. Vaupel: Broken limits to life expectancy.
Science 296: 1029-1031, 10 May 2002.
|