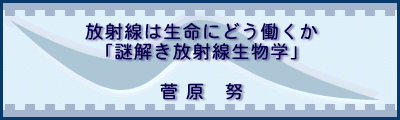 |
|||||||||||||||||||
| 11.放射線で突然変異が生じるとはどういう意味か | |||||||||||||||||||
|
放射線があたるとその生殖細胞に突然変異が生じ、子供に異常が見られることを始めて発表したのは、H.J.Mullerで1927年のことでした。その翌年1928年にAuerbachが化学物質でも同じことが起こることを示しました。これらの研究は何れもショウジョウバエを使ったもので、その後の研究で突然変異にもいろんなものがあり、その頻度がそれぞれに違うことが分かってきました。それを示したものが表11-1です。 表11-1:突然変異の頻度とその相対的頻度
この表で注目してほしいことは、どちらかの親に突然変異が生じたらすぐに子供に見られる筈の優性可視は非常に少ないということです。優性致死が割合に多いですが、これは人では流産するもので次世代への影響としては現れません。それでも、Mullerら遺伝学者が放射線の遺伝的影響を問題としたのは、放射線との間に次のような関係があることが分かったからです。 これによると子供を作るまでに受けた総ての放射線量に比例して突然変異が生じることになるから、大問題であるということです。その後、これはハエの精子についてのことで、ネズミの精原細胞(精子を作るもとで精巣の中で盛んに分裂を繰り返しているもの)では放射線の線量率を下げると突然変異率も下がることが明らかになりましたが、どんなに下げてもゼロになることはありません。従って遺伝的影響は矢張り無視できないことになります。少なくともネズミまでははっきりと認められます。そこで、人について大規模な調査が行われてきました。 ことに日本の原爆被曝者の二世についていろいろの遺伝学的手法を使って研究が続けられています。ここで一つ注意しておきたいことは、人は勿論すべての生物には、放射線を特に当てなくとも自然の突然変異というのが起こっているということです。しかもそれが生物の進化には欠かせないものであると考えられています。普段は邪魔になると考えられる突然変異でも一旦環境に大きな変化があった時にはそれが新しい環境には適合して生き残りに役立つのだ、という訳です。原爆の放射線がこの自然突然変異の上にどれだけ新たな突然変異を付け加えたかを調べることになります。その為にはどうしても統計的な方法にたよらざるを得ません。原爆の場合の他に、放射線科の医師、技師の子供や放射線治療患者の子供についても調べられています。そのどれについても今まで突然変異の増加が証明されたものはありません。 このような事から、最近は人はネズミより精細胞が放射線抵抗性で、突然変異が起きにくく、現在の放射線防護基準で被ばく量が制限されていれば放射線の遺伝的影響は問題にならない考えられるようになりました。すると放射線で一番問題になるのは、子孫ではなく放射線を受けた本人の肉体的影響としての悪性腫瘍(がん)ということになります。がんは遺伝子の病気であるとすれば、同じ突然変異でも体細胞に生じるものが問題であることになります。 体の細胞も次々と分裂を繰り返して増えていくわけですから、その分裂の過程で突然変異を生じることは十分考えられます。次にはこの問題を考えてみましょう。
|
|||||||||||||||||||